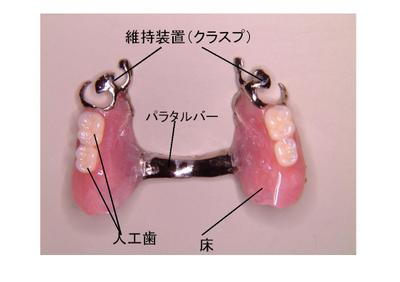今年も6月6、7日と、日本補綴歯科学会学術大会に行ってきました。今回は大阪大学の主幹で、会場は京都国際会議場でした。金曜の診療が終わってから、新幹線を乗り継いで京都駅まで行きましたが、確か前回名古屋に行ったときなどは金曜夜の東海道新幹線は出張か、単身赴任帰りか、混んでいるなという印象でしたが、今年はガラガラでした。ちなみに帰りもずいぶん空いていたのですが、やはり景気が悪いことと、関西方面の新型インフルエンザ、それに休日高速道路1000円の影響でしょうか。
さて、毎年まじめに聴くと非常にしんどい補綴学会ですが、今年も新しい企画として「早朝ミニレクチャー」という講演が2日とも設定され、予め申し込めば朝8時から軽食付きで、各3人関西地方の著名開業医の講師の先生から選んで聴講することができました。さすがにあんまり参加者はいないだろうなと思いながら1日目は茂野啓示先生、2日目は中村公雄先生のレクチャーに参加しましたが、いずれもほぼ満席で、参加者の熱心さというか、もしかしたら食べ物目当てかな、などと思いながら驚きました。
1日目は午前中まずしばらく通常の学会発表があり、それを複数会場はしごしながら聴きました。いつもながら玉石混交というか、思わぬ視点から興味あるものもあればずいぶん詰めが甘い研究もあるのだなと思いました。特に補綴学の扱う対象はたとえばペリオなどと比べて研究を単純化しにくいというか、臨床に即せば即すほど複雑系になってしまい、明快な結果が出にくいのだと思います。見ているとむしろ「科学」であることをかなぐり捨ててしまう方が、新しい一歩を踏み出せるのではないかとも思うのですが。午前の最後に、側方ガイドに関するミニシンポジウムがありました。
昼はランチョンセミナーでまたただ飯を食い、午後は海外特別講演、シンポジウム、臨床スキルアップセミナーと夜7時まで続きます。海外特別講演はアメリカの顎機能異常の権威として有名なオケソン先生のレクチャーですが、何と通訳なしで途中で着いていけなくなり、わかったようなわからないような。今や研究者としてはこの程度の語学は当然なのでしょうか。またシンポジウムはブラキシズムへのチャレンジということでしたが、これが今回の学会でもっともエキサイティングなものでした。
夜終わったときはフラフラでしたが、誰か知ってる先生がいたら一緒に食事へ、などと思っていたのですが、今年も結局会えずじまい。一人寂しく京都の町に向かい、予め調べてあったレコード店に行ってみました。河原町の場末のさびれたレコード店で、その近くの食堂で夕食をとり、しばらく背表紙が光焼けしたCDを眺めました。一応2枚ほど購入し、バスで宿に向かいましたが、そこからしばらく行った盛り場のにぎやか華やかなこと、大失敗だと後悔しながら宿に向かい、寝ました。
2日目も早朝からセミナー、診療ガイドライン作成部会報告「ガイドラインを臨床に生かす」、医療委員会報告「歯周病と補綴歯科治療」、理事長講演、ミニシンポジウム2「無歯顎症例に対するインプラント・・」、ランチョンセミナー、特別講演「食べるということ」、と講演の連続。意識があったり意識をなくしたりの繰り返しで、年々残るものが断片的になってしまいます。この中でガイドラインに関して、地味で歯科全体にはあまり知られていない活動ですが、補綴専門医が拠って立つところというか、補綴学会が社会に発信する根拠というかになる大事なものだと思います。
これらすべての学術大会プログラムの後、別立てで「専門医研修会」がありました。補綴専門医の認定あるいは更新のための研修ですが、今回「この症例にこの補綴処置」という演題で、すれ違い、下顎総義歯の吸着、上顎シングルデンチャー、有床義歯のインプラント、という4つを取り上げ、4人の先生が話されました。特に2、3番目にそれぞれ総義歯で有名な阿部二郎、鈴木哲也両先生が話され、何か対決があるかと期待しましたが、そうでもなかったです。ようやく午後5時にすべてのプログラムが終了しました。
さて今回も母校の先生や同級生に会えるのが楽しみだったのですが、今年はなかなか見つかりませんでした。それでも昨年医科歯科の総義歯の教授になった水口先生、私の2年上で大学のオーケストラでも一緒だったのですが、先生としばらくお話しできたのは一番の収穫でした。また教室の1年上の秀島先生とも会えました。顔を見かけたものの忙しそうで通り過ぎてしまった先生や来ているはずなのに発見できなかった先生もいて残念でした。
残念といえば、今回は漠然と購入を考えているCTの企業展示を期待していたのですが、不景気を反映してか展示のしょぼかったこと。CTどころか大きな機械はぜんぜん来ていない感じで、非常に寂しいものでした。
今回は会場が京都ということで、少しくらいは途中で抜け出してお庭でも見てこようと思っていたのですが、そこまでの元気も無く観光地は横目で見ながら素通りで残念でした。約20年か、非常にしばらくぶりの京都でしたが、駅をはじめとしてずいぶん華やかになった感じでした。また最寄り駅から3時間余りで行けるということを改めて確認し、今度は遊びに来ようと固く誓ったのでした。