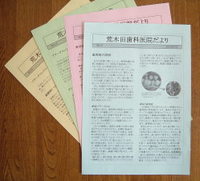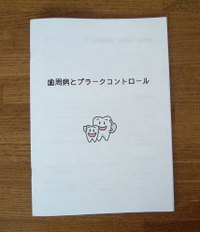私のインプラント事始めその6
このような状況で、まだまだ初心者ながら1歯欠損の臼歯から遊離端ケース、審美の要求される前歯から無歯顎までの様々なケース、骨移植、GBR、ソケットリフト、傾斜埋入、オール・オン4、など様々なテクニックを経験する事ができ、ひととおりの状況には対応できる自信が何とかついてきました。これも、我ながらずいぶん集中して勉強した事と、遅くなって始めた事によってむしろこれまでのベーシックな臨床力が役に立っているのではないかと考えたいです。
さて、ある程度ケースを蓄積してくると、あらためてインプラントの威力をひしひしと感じています。これまで苦労して歯を残し無理をしてブリッジを作ってもあっという間に壊れたり、どうしても義歯が安定しなかったり、大きな義歯床の違和感に悩まされたり、どうしようもなかった事をいとも簡単に解決してしまう場合も少なくありません。整理すると残存歯の犠牲を払わずに補綴できる事、(すれ違い、無歯顎を含めて)遊離端を解決できる事が最大の利点です。そして残念ながらインプラント適応の2つのハードルは、技術的なことよりも経済的な問題と、手術に対する恐怖感だと思います。