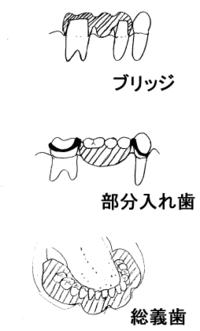臨床歯周病学会26回年次大会
 この土日(6/21・22日)、日本臨床歯周病学会第26回年次大会に行ってきました。会場は千葉県の市川市文化会館、1日目に衛生士部門のプログラムがあったため、今回はうちの衛生士2人を連れて勉強してきました。
この土日(6/21・22日)、日本臨床歯周病学会第26回年次大会に行ってきました。会場は千葉県の市川市文化会館、1日目に衛生士部門のプログラムがあったため、今回はうちの衛生士2人を連れて勉強してきました。
臨床歯周病学会は昨年入ったばかりなのですが、開業医の先生がほとんど中心となって運営している学会で、先々週行ってきた補綴学会とはずいぶん毛色が違います。研究と教育が仕事である大学の人が運営している学会と異なり、自分と同じ開業医の先生方が運営なさっている会なので、いつも申しわけないような気がしています。いつか機会があったら何かの貢献ができればと思っています。
1日目の午前中は会員によるケースプレゼンテーションの発表。やはり研究機関でないだけに、常にノイエス(新しいこと)があるわけではありませんが、臨床医としていろいろ考えさせられる発表が続きます。午後は教育講演として、現在一般の人にも知られている新潟大学教授、安保徹先生の「ストレスと全身との関係」、その理論を取り入れて歯科治療等に生かしている新宿区開業、小西昭彦先生の「ストレスと歯周疾患」でした。安保先生の白血球の自律神経支配の理論は、そこから実際の治療法が書かれている著書も多く、ベストセラーになると同時に批判も多い様です。確かに講演を聴くと何となく納得するのですが、それは大きな流れとして実際の臨床上常に頭に置かなくてはならないことには間違いないものの、実際にそれのみに則って医療を展開していくのは難しい点が多々あると思います。小西先生の講演も同様です。
もちろん患者さんの生き方全体を変えていくことができる医療者になりたいと思いますが、「そもそも論」に陥ってしまう場合が多い。つまり身体に悪い生き方をしたいと思って生活している方はいない、知識の不足や間違いによってそんな生き方をしている場合ばかりではなく、そのような生き方しか出来ない社会に身を置いている場合が多いと思います。だからといってこのような見方をしなくて良いというわけではありませんが、治療の原理として据える事はなかなか難しいと思います。歯周病に限らず、歯科治療に限らず、患者さんの生活全般と病気との関係への介入は、いつも難しい問題を抱えていると思います。
さてこの土曜日は、歯科衛生士部門として別の部屋で講演や講習が行われました。午前中は衛生士のシンポジウムで、「歯科衛生士の業務の変遷と課題」を基調講演とする様々な衛生士像の講演。午後は10種類のセミナーが行なわれました。うちの2人は、「スケーリングスキルアップ講座」「歯肉縁下のプラークコントロール」「メディカルサポートコーチング法のご紹介」に参加しました。特にコーチングの話が新鮮で興味深かったそうです。普段イマイチはっきりしないなどと思っていたうちの衛生士ですが、今回結構楽しそうに勉強したようで、院長として見直した良い機会でありました。
この日の晩は日暮里で開業(たかふじ歯科医院)している同級生の高藤先生と久々に会い、CDショップを経て夕食を食べながら情報交換。2週間前にあの殺人事件のあった交差点を過ぎた秋葉原のホテルに泊まりました。それにしても秋葉原の変わり様には驚きました。小学校の時は交通博物館に、中学の時はラジオの部品を買いに、大学にいた時はCDや実験用の部品を買い求めにと通い慣れた秋葉原ですが、ずいぶん垢抜けた一般向けの(?)町になったような感じです。
2日目は午前午後、特別講演として米国の著名な臨床家であるPamela Kay McClain女史による、「コンビネーション・セラピーを用いた複雑な歯周骨欠損のマネージメント」がありました。歯周治療の究極的な目標である再生療法については、骨移植、組織再生誘導法、エムドゲイン療法などいくつかの手法が知られていますが、その評価と手技上の問題点、また難しい欠損に対するこれらの手法のコンビネーションの症例など、臨床に即した講演でした。術前術後やオペのスライド、エックス線など、眼を見張るような素晴らしい症例群でしたが、すぐに自分でも出来るかと誤解してしまうような危険性がありました。残念ながら実情として患者さんの経済的、また保険治療の問題からなかなか再生療法を試みる機会はないのですが、可能ならどんどんトライしてみたいと思ってはいます。アメリカでは治療費や訴訟の問題が大きいのでしょうが、保存するリスクの大きい歯はどんどん抜いてインプラントにしてしまう傾向にあるようです。日本でもそこにまた保険の問題も絡んできて、自費でインプラントは勧めやすいが再生療法など保存的な治療を自費で行うということは理解されにくい傾向にあると思います。しかし先生もおっしゃっていたように、もう一度安易に抜歯するのではなく何とか保存するようにトライしていくことも歯科の原点として大事ではないかと非常に共感します。
ということで大変充実した2日間でしたが、運営に当たられた先生方に感謝します。また、ここの所疲れがたまっていて、絶対聴かなければと思いながらも意識が薄れていく自分が情けない時間でした。